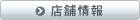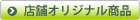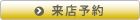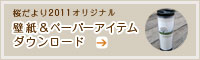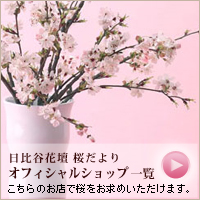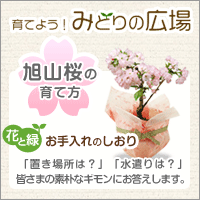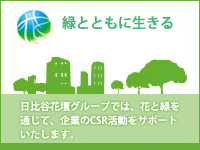東海エリアより、桜の開花情報についてお伝えします。皆様のお気に入りの桜の名所やおすすめスポットをぜひご紹介ください!お待ちしております。
鶴舞公園(つるまこうえん)からの桜だより
2011年March10日
日比谷花壇松坂屋フラワーサロンからお届けする桜だよりは、日本さくら名所100選のひとつ名古屋市昭和区の鶴舞公園からです。

1909年に開園したこの公園は、JR中央本線、地下鉄鶴舞線の駅に隣接する都市公園で、今でこそ街の中心部に
位置する都会のオアシスとなっていますが、開園前は、街外れの沼地を埋め立てたもので1910年の第10回関西府県
連合共進会(博覧会)の会場として整備されたものです。その後一時、動物園が開園していた時期もありましたが、
図書館や名古屋市公会堂が建設され現在では、桜だけでなく、バラや菖蒲など四季折々、花に囲まれた市民の
憩いの場となっています。

公園の名は「つるまこうえん」ですが、その後地名や駅名にあてられた「鶴舞」の文字から、地名や駅名は「つるまい」と
表記されます。園内にはソメイヨシノを中心に約1,000本の桜が植えられ、駅に近いこともありお花見時には、
公会堂横から茶屋までの間は、シートが所狭しと敷き詰められ、花見客でにぎわいます。
昨年は約10万人が訪れたとのことです。


遠くから見ると今はまだ、どこに桜があるのか判別できない状況です。

静かに桜を楽しむなら、公園の奥へ進んだ、竜が池がおすすめとのこと。こちらもソメイヨシノのつぼみは
まだ硬いのですが、春の日差しをあびて輝いていました。例年の見ごろは3月下旬から4月上旬で、
その時期に合わせて18時から21時30分まで夜桜も楽しめるそうです。

岐阜公園からの桜だより(後編)
2011年March09日
さて、本題の桜だよりですが、まずは岐阜公園内で一番最初に咲く桜を紹介しますね。

護国神社の境内にあるこの桜は、通称「鵜飼桜」と呼ばれる彼岸桜で、岐阜公園内で一番早く咲く桜です。
名前の由来は、花のつき方で今年の長良川の「鵜飼漁」が豊漁かどうかを占ったことから。
昔から、生活が長良川と密着した岐阜ならではの由来ですね。でも・・・やっぱりまだつぼみでした。

せっかくなので練習も兼ねて敷地内にあった梅をSHOT!満開の桜をお伝えするまでしばしお待ちあれっ!

岐阜公園のすぐ前にある鵜飼観覧船の造船所がありました。これも岐阜ならではの風景ですね。
造船所内は見学自由でしたので、ちょっとお邪魔してみました。職人さんが真剣に木材を削っていました。
昔の鵜飼漁の風景の模型も展示されていましたよ。ちなみに1300年の歴史がある鵜飼漁をする「鵜匠」は、
代々世襲制なんですって。1300年相伝される伝統漁法の重みを感じました。


最後に岐阜公園一の桜の名所をご紹介します。公園の北側にある「日中友好庭園」です。
異国情緒に溢れる中国式の庭園は新鮮です。三国志好きのNAKAWAPPAにとっては、敵国である呉の美女僑氏を
詠んだ曹操の詩を思い出します。桜が満開時期のこの庭園は、まさに桃源郷の様な・・・(あ、それは桃か)。
桜が散る時期には花びらで埋め尽くされた池がピンクのカーペットの様で、それは美しいと観光案内の方が
教えてくれました。次回は咲いている時期に、より詳しく桜の取材もしますからね。お楽しみに。
岐阜公園からの桜だより(前編)
2011年March09日
寒い冬も終わり、今年も桜の季節がやってきましたね。桜だより岐阜特派員こと、NAKAWAPPAです。
今年は岐阜市内にある桜の名所「岐阜公園」から桜だよりをお届けします。岐阜公園は金華山のふもとにある公園で、
その敷地内には有名な岐阜城や織田信長の居館跡など歴史的な建造物をはじめ、岐阜出身の加藤栄三・東一記念美術館や、
子供が喜ぶ昆虫博物館などがあり、岐阜市民憩いの場として、また観光名所として、広く親しまれている公園です。
今年はそんな岐阜公園を散策しながら、桜の開花情報をお伝えしますね。
さて、駐車場からでて、最初に見つけたのは・・・

なんかコミカルな通称「ロボット水門」です。昭和7年に用水路整備の際に、水防・放水量調節のために造られたもので、
改修時にこんなコミカルな顔になったそうです。でも・・・なんと岐阜県近代化遺産の指定も受けているそうで、
文化的にも評価されているんですって!
水門脇のコミュニティー水路の一角です。涼しげな水音で癒されます・・・仲良く泳ぐ、つがいのカルガモも発見!


織田信長公の若い日の勇壮な銅像が正面入り口に飾られています。岐阜公園内にはこのような水路がいくつもあって、
来園者を和ませます。6月には蛍が楽しめます。
市内にあるとはいえ、金華山のふもとにあるので、野生の動物もいます。それだけ緑豊かな所なんですね。
金華山中腹にある三重の塔。大正天皇がご即位された時の記念として建造された登録有形文化財です。濃尾大震災で倒壊した
長良橋の廃材を利用して造られたそうです。リサイクルですね~。また塔を建てる場所を選んだのは、著名な日本画家
川合玉堂だといわれています。

岐阜公園の北側にある護国神社です。敷地も綺麗に整理されていて身が清まる思いがしました。

そんな護国神社の境内の一角に、な、なんと河童大明神が祀られていました!しかも、まるでゲ○ゲ屋敷
みたいな社殿に河童の置物が・・・なんとも不気味でかわいらしい河童たちです!お賽銭箱も河童をモチーフにしたものです。
製作者?のセンスを感じます。公園と神社の説明が続いたので後編に続きます。
山王日枝神社の桜だより
2011年March07日
全国の桜ファンの皆様こんにちは。今年も桜だよりを担当させて頂くことになりました、日比谷花壇沼津デザインスタジオの
二ペイと申します。今年もよろしくお願いします。昨年は静岡県三島市にある「三嶋大社」から桜だよりをお届け致しましたが、
今年は沼津警察署の近くにあります「山王日枝神社」からお届けします。
日枝神社は慶長5年に鎮座されたと入り口の案内柱に書いてありました。ちなみに慶長5年をネットで調べてみると、
西暦は1600年あの「関が原の戦い」があった年です。静岡県は徳川家康ゆかりの地なので何とも感慨深いものがあります。
この神社はこの近郷近村22箇所を守る役割のために建立されたと記してあります。この「日枝神社」は地元の人には
「山王さん」の名で親しまれています。神社の前の通りは「山王通り」として呼ばれています。案内板にもあるように
この神社は初宮詣~米寿祝まで地域の方々の生活に密着している神社です。親しまれている理由が分かります。

私は現在沼津市の隣町である駿東郡清水町の婚礼施設にお花を納品していますが、
三嶋大社に次いで神前式のお客様が式を挙げる場所としても有名です。
この日枝神社=山王さんがある住所は「山王台」という地名のとおり少し小高いところに
本堂があります。神社の入り口が一番低く、最初の鳥居も数段上にあり、少し見上げる感じになります。
そしてこの鳥居を囲むように桜の枝が腕を伸ばしています。

最初の大きな鳥居を下から見上げると桜の枝模様がキレイに見えます。
その鳥居をくぐり抜け、階段を数段上がると本堂がある場所に出ます。2つ目の鳥居を
手前に右側を見ると小ぶりながら趣のある枝垂桜に出会いました。そして左側に目をやると、
広々とした公園が広がっており、ここにも大きな桜が数本立ち並んでいました。
そのまま左手奥に目をやると「日枝天満宮」と記してある小さなお宮が祭られています。

ここには合格祈願の絵馬が数多くかけられ、その横に梅の花をバックに牛が日向ぼっこをしていました。
私は桜のレポートをこの時期から始めることで、香り立つ梅の花の美しさも再確認しています。

天満宮の手には大きな桜が誇らしげに立っており、優美な枝を伸ばしていました。正面に向きなおして
本堂に目を向けるとその右脇に河津桜が一足先に咲き誇っていました。そして本堂にお参りをして
今年の桜だよりを始めるご挨拶を致しました。


名古屋市堀川御用水跡街園の桜だより
2011年March03日
名古屋市からは堀川沿いの御用水跡街園から桜だよりをお届けします。
名古屋市の中心を流れる堀川は、かつて桜の名所だったそうです。
江戸時代、堀川の桜に心浮き立つ城下の様子を、当時の浮世絵で偲ぶ事ができます。
北区の御用水跡街園は、かつての堀川の面影を留める場所として、とても貴重な場所です。

御用水跡街園は城内の飲用水として、そしてお殿様の避難経路として存在していた用水路だったそうです。
避難経路であった証の大きな松を、黒川樋門近くで見つけました。

明治時代には、御用水に平行する黒川を造り、行商船が往来した事もあったのだそう。
現在では堀川沿い御用水跡街園の1.5キロを、ソメイヨシノ、山桜、八重桜、枝垂れ桜、薄墨桜など
約600本の桜が咲きほこる川へと変貌を遂げました。

2月下旬、土手にたくさんの水仙が咲いていました。

川底には、カワニナ、マシジミがのんびり動いています。黒川1号橋の近くの四季桜が、冬を越えて
最終の花を咲かせていました。春はもうこの川に訪れている事を感じる事ができました。